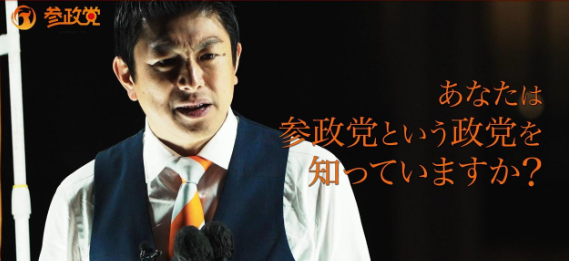
Gemini 2.5 Flash
2025年7月22日
参政党は、2020年4月に神谷宗幣氏を中心に結党された日本の政治団体です。
結党から国政進出まで
-
結党と理念: 2020年4月、既存の政治への危機感を持つ有志が集まり、「国民が政治に参加する党」としてゼロから結党されました。特定の支援団体や資金源を持たず、国民の知恵と資金で運営されています。
-
国政初挑戦: 2022年の参議院選挙で国政に初挑戦し、比例区で神谷宗幣氏が当選し、国政政党となりました。約177万票を獲得し、この時点で「一発屋政党」との見方も一部にありました。
-
地方議員の拡大: 国政進出後も、全国に支部を広げ、地方議員の数も増やしていきました。2024年10月の衆議院選挙では比例で3議席を獲得し、地方議員は140名以上を数えるようになりました。
2025年参議院選挙後の状況
躍進と議席増: 2025年7月の参議院選挙では、議席を大幅に伸ばし、非改選と合わせて11議席以上が確実となりました。これにより、参議院で予算を伴わない法案の提出が可能となりました。
「日本人ファースト」の主張: 「日本人ファースト」を前面に掲げ、減税と積極財政、外国人受け入れ制限などを訴え、幅広い層(自民党の支持層、就職氷河期世代、無党派層、主婦層など)から支持を得ています。
主要政策:
- 教育・人づくり: 学力だけでなく、自ら考え学ぶ力を育む教育、国や地域、伝統を大切にする自尊史観の教育を重視しています。現代版師範学校の創設や教員の待遇改善なども掲げています。
- 食と健康・環境保全: 化学物質に依存しない食と医療の実現、循環型農業の推進、食料自給率の向上(特に米の増産・輸出奨励)、食品表示法の改善、オーガニック給食の推進などを訴えています。昆虫食や培養肉ではなく、和食の良さを発信し米食を推進しています。
- 国のまもり: 日本の舵取りに外国勢力が関与できない体制づくりを重視し、外国資本による企業買収や土地買収の規制、外国人労働者の増加抑制、外国人参政権への反対などを掲げています。
- 経済政策: 国民負担率を上限35%に抑え、減税と社会保険料削減で手取り収入を増やすことを目指しています。人工知能、製造業、サブカルチャーを「三本の矢」として重点的に支援し、日本の再興を図るとしています。消費税の段階的廃止も主張しています。
国会での活動: 国会では、日銀の金融政策や政府の財政政策、外国人受け入れ政策、中小企業支援、能登半島地震の復興支援などについて積極的に発言しています。
今後の展望: 神谷宗幣代表は、現時点で与党と組むことは否定しており、まずは次の衆院選に向けた態勢を固め、国会での発言力をさらに強めていく方針です。また、スパイ防止法案の国会提出に向けた準備も進めています。
参政党は、インターネットを中心とした政治活動から始まり、全国に支部を広げ、街頭演説やSNSを活用して支持を拡大してきました。その単純明快な主張は、既存政党への不満を持つ層に響き、今後の政界に影響を与え続けていくとみられています。
Copilot
2025年7月22日
参政党は比較的新しい政党ですが、その歩みはとてもユニークで、近年の日本政治に新しい風を吹き込んでいます。以下に、過去から現在までの流れをわかりやすくまとめました。
🏁 起源と結党の背景(2019〜2020年)
- 前身はYouTubeチャンネル「政党DIY」 神谷宗幣氏(元吹田市議)が中心となり、政治や社会問題を発信するチャンネルを開設。多くの支持者を獲得しました。
- 2020年4月に正式に結党 「投票したい政党がないなら、自分たちでゼロからつくる」という理念のもと、参政党が誕生しました。
📈 国政進出と躍進(2022年)
- 2022年参議院選挙で初の国政進出 比例区で約177万票(得票率3.3%)を獲得し、神谷氏が当選。政党要件を満たし、国政政党となりました。
- SNSや街頭演説を駆使した選挙戦術 YouTubeやタウンミーティングを活用し、無党派層や若年層から支持を集めました。
🧭 現在の状況(2023〜2025年)
議席数と組織拡大 2025年時点で、国会議員5名(衆院3・参院2)、地方議員151名、全国287支部を展開。
代表は神谷宗幣氏 党の顔として全国で街頭演説や講演を行い、SNSでも積極的に発信しています。
主な政策と理念
- 「日本人ファースト」
- 教育改革(歴史教育の見直し、道徳教育の充実)
- 食の安全(有機農業推進、食品添加物規制)
- 積極財政・減税
- 参加型民主主義(DIY政党)
最近の動向
- 2024年衆院選で比例代表3議席を獲得
- 東京都議選でも複数議席を確保
- 参院選2025では全選挙区に候補者を擁立予定
⚠️ 課題と批判も
- 党内分裂や離党者の増加 創設メンバーの一部が離党し、「独裁的な運営」への批判も出ています。
- 一部政策への懸念 反ワクチン、反グローバリズム、排外主義的な主張などが議論を呼んでいます。
興味深いのは、参政党が「保守」と「市民参加」を融合させた独自のスタイルを築いている点です。今後の選挙でどこまで支持を広げるか、注目ですね。
ChatGPT
2025年7月22日
【参政党の過去】
1. 結党と背景(2020年)
参政党は2020年に結成され、保守的・ナショナリズム的な立場を取りつつ、既存政党に対する不満を取り込む形で台頭しました。SNSやYouTubeを積極活用し、主に若年層や無党派層にアプローチ。
-
創設メンバーには、神谷宗幣(元吹田市議・元大阪府議)、武田邦彦(元中部大学教授)、吉野敏明(歯科医師)など、著名人や知識人が名を連ねました。
2. 主張と理念
以下のような主張が特徴です:
- 「教育・食・健康」重視:食の安全や自然医療に関心が強い。
- 国防・歴史教育の強化:日本の伝統文化・歴史への誇りを持たせる教育を主張。
- グローバリズムへの批判:脱GHQ体制や国際機関の影響への反発。
これらは、コロナ禍中の政府対応への不信感を背景に、支持層を広げました。
3. 2022年参議院選挙での躍進
- 初の国政選挙となった2022年参院選で比例区から1議席(神谷宗幣)を獲得し、注目を集めました。
- 「泡沫政党」扱いされながらも、YouTubeの街頭演説動画で数十万〜百万回再生されるなど、ネット選挙で存在感を見せました。
【参政党の現在(2025年時点)】
1. 党内の分裂と対立
- 2023〜2024年頃から、党運営や資金管理、意思決定に関して党内で不満が表面化。
- 神谷宗幣のリーダーシップに対し、「独裁的」「不透明」とする批判が一部から出て、吉野敏明ら創設メンバーが離党・対立を表明する事態となりました。一部メディアでは「参政党の乗っ取り騒動」と報道。
2. 資金と組織運営の問題
- 党所属議員や候補者が党に「収入の1割を納入」する制度に対して不満を持つ者も多く、「金銭的拘束が強い」との批判あり。
- 政治資金の使途の不透明さも一部で問題視されました。
3. 現在の活動と立ち位置(2025年)
- 引き続き、街頭演説・SNS中心に支持拡大を図るスタイルを維持。
- ただし、党の内部分裂・支持層の固定化により、2025年の地方選挙や参院選では勢いが鈍化傾向との指摘もあります。
- 一部では、「陰謀論的な主張が強すぎる」「現実政治との乖離がある」とする批判も増えています。
【まとめ】
| 時期 | 主な特徴 |
|---|---|
| 2020年 | 結党。保守層・ネット層をターゲットに始動 |
| 2022年 | 参院選で神谷宗幣が初当選し、国政入り |
| 2023年以降 | 党内対立、創設者の一部が離脱 |
| 2025年現在 | 神谷体制継続中も、勢いに陰り・体制内外から批判も |
DeepSeek R1
2025年7月22日
Gemini ー Deep Reseach
2025年7月22日
参政党の過去と現在:その軌跡と政治的影響力の分析
はじめに
参政党は、既存の政治に対する強い危機感から有志の国民によって2020年4月11日に設立された国政政党である 。特定の支援団体や資金源を持たず、「子供や孫の世代によい日本を残したい」という共通の思いを持つ一般の国民が集まって活動を続けている点が特徴である 。
本レポートは、参政党の結党から現在に至るまでの軌跡を詳細に分析し、その理念、政策、選挙結果、支持層、そして日本の政治地図における影響力を多角的に考察することを目的とする。
第1章 参政党の結党と初期の歩み
1.1 結党の背景、理念、および綱領
参政党は、「今のままの政治では日本が日本でなくなってしまう」という強い危機感から生まれた政治勢力である 。この背景には、既存の政治システムや主要政党に対する国民の不満、そして特定のイデオロギーに偏らない新しい政治的選択肢への潜在的な需要の高まりがあったと考えられる。
党は2020年4月11日に正式に設立されたが 、その前身は、2019年4月に神谷宗幣氏らが開設したYouTubeチャンネル「政党DIY」である 。このチャンネルは約1年間で社会問題や政治に関する50以上の動画を公開し、約4.5万人のチャンネル登録者を集めた 。従来の政党設立プロセスが組織や資金力を基盤とするのに対し、参政党がYouTubeチャンネルを母体として結党された事実は、インターネットとSNSが現代の政治活動において強力なツールとなり得ることを示している。特に、既存メディアへの不信感を持つ層や、政治に関心が薄い若年層へのリーチに成功した可能性が高い。この「オンラインからオフラインへ」の動員モデルは、現代の政治運動における新たな潮流を形成し、後の草の根運動や選挙戦での支持拡大に繋がる重要な要因となった。
参政党の理念は「日本の国益を守り、世界に大調和を生む」ことを掲げている 。これは、自国の利益を最優先しつつも、国際的な調和を目指すという姿勢を示唆する。党の綱領は以下の3つの柱から構成される 。
- 先人の叡智を活かし、天皇を中心に一つにまとまる平和な国をつくる。
- 日本国の自立と繁栄を追求し、人類の発展に寄与する。
- 日本の精神と伝統を活かし、調和社会のモデルをつくる。
綱領に「天皇を中心に一つにまとまる」「先人の叡智」「日本の精神と伝統」といった言葉を明確に盛り込んでいることは、既存の保守政党が十分に訴求できていないと感じる層、特に伝統的価値観を重視する層へのアピールを意図していると分析できる。近年の社会の多様化やグローバル化への反動として、自国のアイデンティティや伝統を再評価しようとする動きがある中で、参政党のこの綱領はそうした層のニーズに応えている。既存政党が多様性やグローバリズムに傾倒する中、伝統的価値観を重視する層の政治的「受け皿」が不在であった状況において、参政党が明確な「国柄」重視の姿勢を打ち出すことで、特定の保守層からの支持獲得に成功したとみられる。
表1:参政党 理念・綱領
| カテゴリ | 内容 |
| 理念 | 日本の国益を守り、世界に大調和を生む。 |
1.2 設立メンバーと初期の活動
参政党の主要設立メンバーには、神谷宗幣氏が中心となり、KAZUYA、渡瀬裕哉、筱原常一郎、松田学といった面々が名を連ねている 。神谷宗幣氏は、元吹田市議会議員であり、ネットチャンネル「CGS」を開設して政治、歴史、経済をテーマに発信を続けてきた人物である 。神谷宗幣氏が10数年以上にわたり一貫した思想と構想力で地方政治から国政を見据えてきた「筋金入り」の政治家であるという指摘は 、党の理念や政策の安定性と深みを示唆している。彼の「思想が肉体に憑依したような迫力」という表現 は、カリスマ性や求心力が党の成長に大きく寄与していることを示している。既存政党のリーダーが政策調整や派閥力学に追われる中で、神谷氏のような「思想家」としての側面を持つリーダーが、明確なビジョンとメッセージで支持者を引きつけるという構図が認められる。
初期の活動では、「政党DIY」というユニークなコンセプトを掲げ、街頭演説、SNS、YouTubeなどを活用し、既存政党とは一線を画すコミュニケーション手法で支持を広げていった 。この手法は、特定の支援団体や資金源を持たない党にとって、国民との直接的な対話を重視し、草の根の支持を築く上で不可欠であった。この「政党DIY」というコンセプトは、単なるスローガンではなく、党員やサポーターが政策立案や活動に積極的に参加することを促す仕組みとして機能している 。これにより、党は「国民の手に政治を取り戻す」という理念を実践し、既存政党への不信感を持つ層の共感を深めた。政治への不満が「どうせ変わらない」という諦めにつながる中で、「自分たちで政治を作る」という参加型のアプローチは、有権者の政治的エンゲージメントを高める効果を持つ。
第2章 参政党の政策の変遷と現状
2.1 主要政策の柱と具体策
参政党の政策は、国民が「この国に生まれてきてよかった」と実感できる社会を目指し、7つの分野にまとめられている 。特に「教育・人づくり」「食と健康・環境保全」「国のまもり」の3つが重点政策として強調されている 。
-
教育・人づくり: 参政党は、「学力(テストの点数)より学習力(自ら考え自ら学ぶ力)の高い日本人の育成」を目指している 。具体的な施策として、経済格差が教育格差を生む連鎖を断ち切るため、0〜15歳への月10万円の子育て教育給付金(教育国債を財源とし、子供一人ひとりに支給)や奨学金給付制度の拡充を重視する 。また、子供の個性に寄り添った多様な教育環境の整備(フリースクール、スクールチョイス、少人数化)や、日本人にとって大切なこと(国の成り立ち、偉人の功績、神話、歴史、郷土愛、家族愛)を教える教育を推進している 。スマートフォンの長時間利用が子供の脳の発達や睡眠に与える悪影響を懸念し、デジタル機器の利用制限の必要性も提唱している 。
-
食と健康・環境保全: 「化学的な物質に依存しない食と医療の実現と、それを支える循環型の環境の追求」を目指している 。食料自給率100%(2050年目標)を目指し、米の増産・輸出奨励、種子・化学肥料の自給率向上、遊休農地活用、適正関税賦課を推進する 。食料備蓄体制の強化として、1年分の食料を全市区町村に確保することも掲げる 。医療分野では、対症医療から予防医療への転換を提唱し、無駄な医療費削減と健康寿命延伸のため、診療報酬制度の見直しや予防医療へのインセンティブ導入を訴える 。新型コロナワクチン接種推進策の見直し(子供への接種中止、大人への完全任意化、補助金見直し)や、ワクチンの安全性・副反応に関する包括的な情報提供も求める 。自然生態系の保全を重視し、環境破壊に繋がる再生可能エネルギー開発(メガソーラー・風力発電)の見直しを主張しており 、昆虫食や培養肉よりも和食・米食の推進を掲げている 。
-
国のまもり: 「日本の舵取りに外国勢力が関与できない体制づくり」を目指す 。国民負担率35%を上限とし、消費税の段階的廃止、社会保険料減額による手取り収入増を推進する 。財政収支の黒字化目標を見直し、積極財政による経済成長で国民生活を豊かにする方針を打ち出している 。金融中心の経済から実体経済中心への回帰、働く人々への適正な利益分配を重視し 、インボイス制度の即時撤回を求める 。また、「働き方改革」と「年収の壁」の見直し(年収の壁212万円への引き上げ、時間外労働上限規制緩和)も主張する 。国防面では、自立的な防衛確立、対等な日米同盟、核抑止力の保有、外国人による土地・インフラ買収の制限、日本版「スパイ防止法」の制定、外国人総合政策庁の設置などを提唱している 。
参政党の政策は、「日本人ファースト」というスローガン を核に、教育、食、健康、経済、国防、外国人政策など多岐にわたる分野で具体的な施策を提示している 。これは、単なる排外主義ではなく、日本の自立と国民の生活向上を包括的に目指すというメッセージとして、幅広い層に響いている 。既存政党がグローバル化や多様性を推進する中で、参政党は「内向き」とも捉えられかねない「日本人ファースト」を掲げつつも、それが国民の具体的な生活不安(食料、医療費、経済格差、外国人問題)に直結する政策と結びつくことで、有権者の共感を呼んでいると分析される。
表2:参政党 主要政策概要
| 政策分野 | 目標 | 具体策(抜粋) |
| 教育・人づくり | 学習力重視、自国に誇りを持つ教育、スマホ悪影響からの保護 | 月10万円子育て教育給付金、スクールチョイス、少人数教育、歴史・文化教育、デジタル機器利用ガイドライン |
| 食と健康・環境保全 | 食料自給率100%、予防医療、自然生態系保全 | 米の増産、種子・肥料自給率向上、有機栽培促進、予防医療インセンティブ、ワクチン接種見直し、再エネ開発見直し、和食・米食推進 |
| 国のまもり | 国民負担率35%上限、積極財政、デジタル主権確立、自立防衛 | 消費税段階的廃止、社会保険料減額、財政法4条改正、インボイス即時撤回、年収の壁見直し、スパイ防止法、外国人総合政策庁設置 |
2.2 政策の進化と重点の変化
参政党の政策は「今後も、党員自ら立案し、追加・更新していきます」と明記されており , 「政党DIY」のコンセプトを政策面でも実践していることを示している。
設立初期の政策は、COVID-19対策への強い批判に焦点を当てていた点が特徴的であった 。具体的には、「戴口罩自由化」「COVID-19分類引き下げ」「無症状者PCR検査廃止」「経済社会活動正常化」「国外入境制限廃止」「緊急事態条項反対」「パンデミック条約反対」「ワクチン接種任意化」などが挙げられる 。
第3章 選挙結果に見る参政党の躍進
3.1 国政選挙での実績
参政党は、国政選挙において短期間で顕著な実績を上げている。
- 2022年参議院議員選挙: 国政に初挑戦し、比例区で1議席を獲得した 。この選挙での得票数は約177万票に達した 。愛知選挙区で杉本純子氏が約53万票を獲得して当選し 、大阪選挙区でも宮出千慧氏が当選するなど 、地方選挙区でも存在感を示した。
- 2024年衆議院議員選挙: 94人の候補者を擁立し、比例区で187万票を獲得し、3名が国会へ進出した 。
2020年設立の比較的新しい政党が、2022年の参院選で1議席、2024年の衆院選で3議席を獲得したことは、日本の政治において既存政党への不満が根強く、新たな政治勢力への期待が高まっていることを如実に示している。特に、特定の支援団体を持たない草の根の活動でこれを達成した点は注目に値する。既存政党の支持率低迷や、特定の争点(例:外国人問題、物価高)に対する明確な立場を示せない状況が、新興政党の躍進を後押ししていると分析される。
表3:参政党 国政選挙結果推移
| 選挙名 | 獲得議席数(内訳) | 得票数 |
| 2022年参議院議員選挙 | 1 (比例区) |
約177万票 |
| 2024年衆議院議員選挙 | 3 (比例区) |
187万票 |
3.2 地方選挙での拡大と組織基盤
参政党は国政だけでなく、地方選挙においても着実に議席を増やし、組織基盤を強化している。
- 統一地方選挙での躍進 (2023年): 統一地方選挙の後半戦で93名が当選し、前半戦の県議4名、政令市議3名を合わせ、合計100名の地方議員が誕生した 。統一地方選挙前は31名だった地方議員が、この結果を通じて合計124名に増加した 。
- 継続的な地方での当選: 2022年9月以降、沖縄市議選、兵庫県川西市議選、新潟県燕市議選、青森市議選で「4連勝」を達成し、いずれも30代の男性候補が当選した 。その後も桑名市議選、松戸市議選で公認候補が当選 。2025年には尼崎市議選でトップ当選 、那覇市議選、奈良市議選、石川県議会補選、美郷町議選でも当選者を出している 。
地方選挙における議席の着実な増加は、党が全国的な組織基盤を強化していることを示している。地方議会での議席獲得は、党の政策実現能力の証明、党勢の維持・拡大、そして将来的な国政選挙での足がかりとなる。地方自治体が抱える具体的な問題(例:食料、医療、教育)に対して、既存政党が画一的な対応しかできない中で、参政党が地域に密着した政策や草の根運動を展開することで、地方の有権者の支持を得ているとみられる。
参政党の高い勝率は、全国の市町村ごとの「基礎票」データを分析した選挙戦略と、党員数の急増に支えられている 。党員数はサポーターを含めて約10万人に達し、その多くは30~50代の働き盛り世代で、熱心に活動に参加している 。
今後の目標として、来年の統一地方選挙では全国で494人の候補者擁立を目指しており、次期衆院選でのさらなる党勢拡大を狙っている 。
表4:参政党 地方議員数推移
| 時期 | 地方議員数 |
| 統一地方選挙前 (2023年) |
31名 |
| 統一地方選挙後 (2023年) |
124名 (うち統一地方選挙で100名当選) |
| 現在 (2024年以降の地方選含む) |
約150名 |
第4章 参政党の支持層と世論の評価
4.1 支持層の内訳と特徴
参政党は、保守層を中心に幅広い支持を集めている 。特に、自民党への不満を持つ層の受け皿となり、岩盤保守層を切り崩している側面がある 。
支持政党がない「無党派層」の比例投票先においては、立憲民主党、自民党に次いで3番目に高い支持を得ており 、特に保守系・右派系の無党派層からの支持が厚い 。また、参政党は右派政党のような雰囲気がありながらも、経済政策には左派的な部分も見られるため、れいわ新選組の支持層から参政党に流れる傾向も観察される 。
年齢層別では、60代以上の高齢層よりも、40代-50代の割合が高く、さらに「40代以下」で5割を超えており、比較的若い層からの支持も厚い 。就職氷河期世代や主婦層にも支持が広がっている 。
支持層が重視する政策としては、「外国人の受け入れ問題」を挙げる層からの投票割合が最も高い 。物価高対策では「消費税減税」への支持が強い 。
参政党が、自民党支持層の一部、無党派層、そしてれいわ新選組支持層の一部といった多様な層から支持を得ているのは、既存の主要政党が十分に拾いきれていない国民の不満や不安の「受け皿」となっているためである 。特に「外国人受け入れ問題」のように、既存政党が明確な立場を示しにくい争点を巧妙に設定している点が奏功している 。政治的イデオロギーの左右という従来の軸では捉えきれない、より生活に密着した不安や、ナショナリズム的な感情が、新たな政治勢力への支持を形成しているとみられる。
表5:参政党 支持層の属性と重視政策
| 属性 | 特徴 | 重視政策 |
| 支持層の属性 | 保守層、自民党への不満層、無党派層(保守系・右派系)、れいわ新選組支持層の一部、40代以下、就職氷河期世代、主婦層 | 外国人受け入れ問題、消費税減税 |
4.2 肯定的な評価と支持される理由
参政党が支持を拡大している背景には、いくつかの要因がある。神谷宗幣代表の歯切れの良い演説と、「日本人ファースト」という分かりやすいスローガンが幅広い層に響いている 。彼の発言は「本音を言う政治家」への期待に応えているとの指摘もある 。
また、YouTubeやX(旧Twitter)を活用した動画や投稿が、若年層や政治に関心が薄い層に広くリーチし、短時間の切り抜き動画がSNSで拡散され、認知度を急上昇させた 。党員による街頭演説など、草の根の活動も支持拡大に寄与している 。
4.3 批判的評価と論争の背景
参政党は、その急速な台頭と独自の主張により、様々な批判に直面している。
「日本人ファースト」というキャッチコピーは排外主義につながるとの懸念が根強い 。神谷代表は「外国人差別と言われるが、そういう言い方は一切していない」と否定しているが、具体的な発言(例:「仕事に就けなかった外国人が、万引きとかして大きな犯罪が生まれている」「出稼ぎに来ている外国人のいろんな社会保障まで日本が全部丸抱えするのは、明らかに過剰だ」)が批判の対象となっている 。
4.4 神谷宗幣氏の発言と党への影響
神谷宗幣氏は参政党の代表であり、その発言は党のイメージと支持に直結する 。彼の「日本人ファースト」というキャッチコピーは、党のアイデンティティを形成する上で極めて重要である 。
第5章 参政党の政治的立ち位置と今後の展望
5.1 他党との関係性と日本の政治地図への影響
参政党は、自らを「中道寄り」の立場を取り、左右どちらにも偏らない政策を進めていると説明している 。しかし、その政策綱領や具体的な主張(例:保守主義、右翼民粹主義、日本民族主義、反グローバリズム、反移民、天皇中心主義)からは、強い保守的・右派的な色彩が見て取れる 。この「複雑な性質」が、多様な支持層を引きつける要因となっている 。
参政党の躍進は、日本の政治地図に以下の変化をもたらす可能性があると専門家は分析している 。多党化の進行を加速させ、二大政党制から多党制への移行を促す可能性がある。また、従来とは異なる争点(例:外国人受け入れ問題、ワクチン政策)の政治的重要性を高め、政策論争の多様化を促す。さらに、政権運営における新たな変数を生み出し、連立の複雑化を招く可能性も指摘される。
参政党は、既存の主要政党が避けてきた、あるいは明確な立場を示してこなかった「外国人問題」などの争点を巧みに設定し、これを主要な政治課題として浮上させた 。これにより、他党もこれらの問題に対する明確な対応を迫られることになり、政治議論の多様化を促している。日本中央大学教授の中北浩爾氏は、多くの有権者が自民党と最大野党である立憲民主党を「古すぎる」と感じ、参政党のような「新鮮さ」と草の根の動員力を持つ新興政党に票を投じていると指摘している 。日本国際大学副教授の山口真一氏は、参政党がSNSを通じて世論を突破し、「オンラインが現実を牽引する」効果を生み出したと分析している 。
5.2 参政党が直面する課題と将来の方向性
参政党は、その成長と影響力拡大に伴い、いくつかの課題に直面している。
- 政策実現能力の証明: 議席を獲得したものの、支持者の期待に応える具体的な政策実現が求められる 。少数政党として、国会での影響力を発揮するためには、戦略的な他党との連携も必要となる。
- 党勢の維持・拡大: 一時的な支持から持続的な支持基盤を構築する必要がある 。特に、多様な意見を持つ党内での意見集約と、統一的な政策決定の難しさが課題となり得る 。
- 批判への対応: 「排外主義」や「陰謀論」といった批判に対し、どのように社会的な理解を得ていくかが問われる 。神谷代表は批判を「追い風」と捉えているが、これが長期的な党の信頼性や支持拡大にどう影響するかは注視が必要である。
- 内部対立の克服: 過去には党内の混乱や分裂騒動があったものの、組織再編と理念の明確化により信頼を回復し、地方議会で存在感を高めている 。今後も組織のガバナンスが問われる。
将来の方向性として、参政党は「創憲」を提唱している。「護憲」でも「改憲」でもなく、国民自身がゼロから新しい憲法を創ることを目指し、国民の意識改革と政治への主体的な関与を促すことを目指している 。経済面では、名目成長率4%の経済実現(インフレ目標2%+実質成長率2%)を掲げ、積極財政や情報技術実装、コミュニティ型生産環境の構築を重視している 。また、地方創生の強化や、より実践的な教育システム導入など、具体的な政策を立案し実行に移す姿勢を示している 。
参政党は、設立当初から「国民運動」としての側面を強く持ち、既存の政治システムへの不満を背景に支持を拡大してきた。しかし、国政や地方議会で議席を獲得し、影響力を増すにつれて、単なる批判政党ではなく、「政策実現能力」を持つ「政権選択肢」としての役割が求められるようになる。この転換期において、党内の多様な意見の集約や、具体的な政策の実行力が試されることになる。理念の純粋さを保ちつつ、現実的な政治運営を行うバランスが重要となる段階にある。
結論
参政党は、2020年の結党以来、「日本の国益を守り、世界に大調和を生む」という理念と、天皇を中心とした伝統的価値観を重視する綱領を掲げ、独自の道を歩んできた。YouTubeチャンネルを母体とした「政党DIY」という革新的なアプローチは、既存政治への不満を抱く幅広い層、特に若年層や無党派層の支持を獲得する上で大きな成功を収めた。
2022年参議院選挙での1議席獲得、2024年衆議院選挙での3議席獲得、そして統一地方選挙での地方議員数の大幅な増加は、参政党が日本の政治地図に新たな変数をもたらしていることを明確に示している。食料自給率100%達成、予防医療への転換、積極財政、外国人政策の見直しなど、「日本人ファースト」を掲げた具体的かつ生活に密着した政策は、国民の不安や不満に直接訴えかける力を持っている。
一方で、その主張は「排外主義」や「陰謀論」との関連を指摘され、批判の対象となることも少なくない。しかし、神谷宗幣代表はこれらの批判を「追い風」と捉える姿勢を示しており、この逆説的な構造が党の結束を強める要因ともなっている。
参政党が今後、単なる「不満の受け皿」から「政策実現能力を持つ政党」へと進化できるか、そして内部の多様な意見をまとめ上げ、持続的な支持基盤を構築できるかが、その将来を左右する鍵となる。日本の政治の多党化が進む中で、参政党の動向は、今後の政策論争の多様化や連立の複雑化に大きな影響を与えるものと予測される。